昨年末に、「この案件、なぜ自分に依頼が来たんだろう?」と思う案件が来た。
そう思いながらも全力で対応して、二度と依頼が来ることは無いだろうと思っていた。
また最近、同じ会社の同様の案件が来た。お主、チャレンジャーやな。
前回の翻訳は問題なかったのだなと安心しながらも、前回以上に調査を行って納品した。
二度あることは三度あるではないが、継続して依頼が来るようであれば、新規分野としてちゃんと勉強しよう。
翻訳者であれば大抵は自分の対応分野を持っていると思う。
自分の場合は、ITとメディカルをメインとしているが、最近は圧倒的にITの依頼が多い。
私の経歴からすると、依頼する側からしても、IT分野の翻訳の方が納得感はあると思う。
自分としても、内容の理解や訳出する上で、最後の最後まで粘りを出せるのはIT分野だと思っている。
実務での修羅場もくぐっているし、現場で陥りがちな原文の間違いを自信をもって指摘できる。
自分が現場を知らない実務分野だと、明らかな誤り以外はスルーして原文通りに訳すしかない。
程度の問題はあるが、翻訳者としては仕方ないことだとは思う。
でも、実務翻訳の場合は、できれば原文を書いた人と同じ程度に実務分野のことが分かっている人が翻訳する方が望ましいと思っている。もちろん、文書の種類に応じて、そこまで必要ない場合もいっぱいある。
私は若い人が将来は実務翻訳者になりたいと言うのであれば、最初はIT、メディカル、法務など、自分が目指そうとする分野の実務ができる会社に入って、「私、英語が得意です」とことあるごとにアピールするとよいとアドバイスする。
そうすると、何か英語が関連する仕事が発生すると、声がかかる可能性が高くなる。
そういうことを繰り返すと、日本語でも英語でも実務の表現が身についてくる。
この話をするときの落ちとしては、「そうやって頑張るうちにその仕事が面白くなって、翻訳者になりたかったことなど忘れてしまうのが一番」と言っているのだが、51%以上本気でそう思っている。
対応分野を広げる話に戻ろう。
翻訳者が新しい分野に対応したいとか、分野を変更したいという場面はあるかもしれない。
対応していた分野の案件が少なくなってきたとか、単価が低くなってきたとかいろいろ理由はあるだろう。
でも、自力で新しい分野を開拓するのは、結構大変だと思う。私もメディカル分野ではそう感じてきた。
新規分野が必要だと思っている場合、「翻訳の分野を増やしたり変えたりすることで、今ぶち当たっている問題が本当に解決されますか?」ということを考えてみるのも良いのではないだろうか。
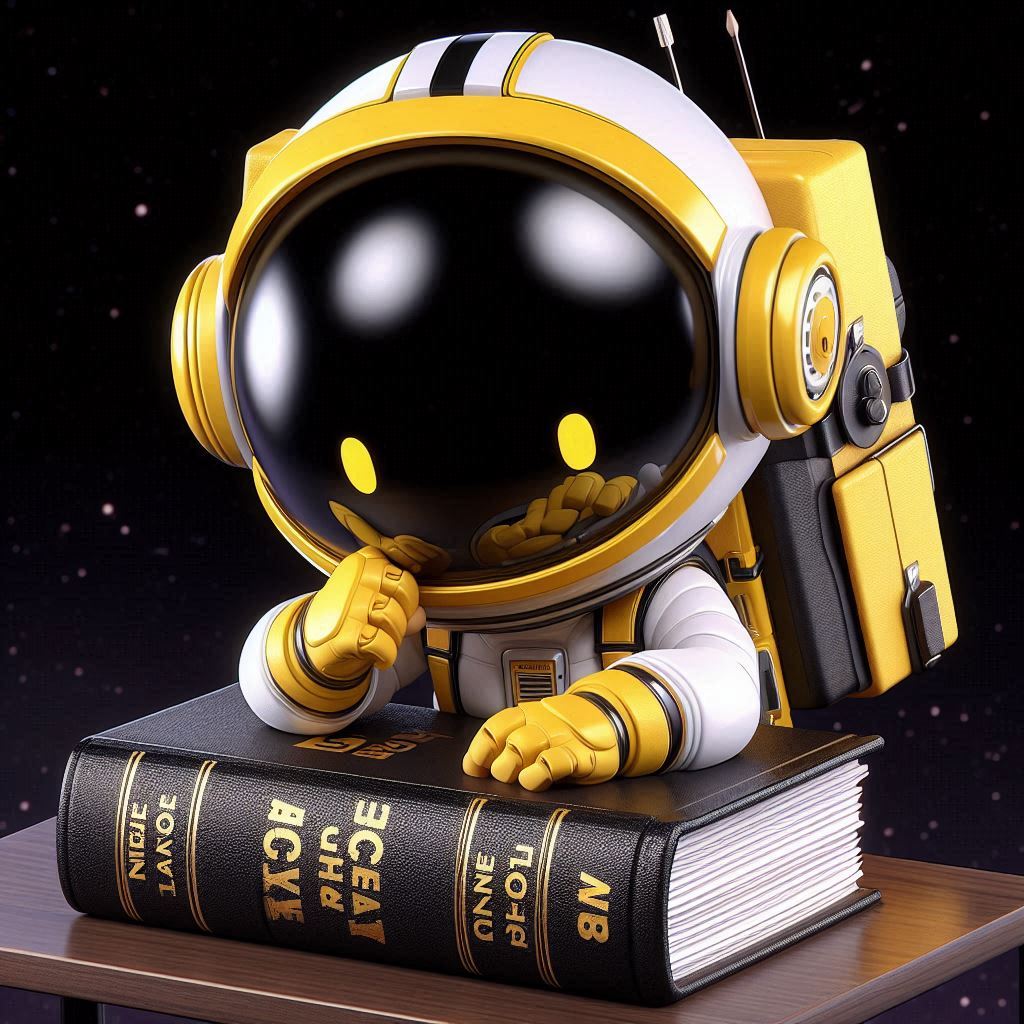
コメント